
ご覧いただきありがとうございます。
このブログの内容
小学校の通常学校で行う発達障害がある子・周りの子も輝く特別支援教育
あなたが得られること
①実例別の行動の原因と対応法
②周りの子からも不満が出ない指導法
③深刻な二次障害への対応策
※この記事は単独ではなく、今までの記事、これから連載される記事と関連づけられています。
信頼性
私は、小学校教諭を定年退職しました。
その後も再任用、講師としてフルタイムで継続して勤務しています。
学級担任、少人数指導、特別支援学級担任を経験させていただきました。
現在も、特別支援学級担任として勤務しています。
そこでの実践を生かし、知見したことに基づいて吟味した情報を発信しています。
さっそく、前回の続きを見ていきましょう。
今回は、19回目になります。
過去のブログを合わせて見ていただきますと、より理解が深まります。

実例11 ☆☆☆ 運動会の参加が難しい ☆☆☆ (特性:広汎性発達障害)
【なぜそうなるのか?】
●ボディーイメージがつかめない
ダンスなどの運動の苦手な子は、ボディーイメージがつかめていない可能性があります。
ボディーイメージとは、自分の身体の大きさや動きを把握することによってできる、自分の身体のイメージ像のことです。
例えば、音楽や指示にあわせて、素早く体を動かすことができなかったり、縄跳びでジャンプするタイミングが分からず、すぐにひっかかってしまったりします。
そんな子を見て、周りの子どもたちが、からかったりすることも起こってきます。
また、発達障害がある子のなかには、疲れやすい子、筋力が弱い子、同じ姿勢を保つことが困難な子もいますので、運動会や体育でどう参加させていくかが重要です。
【個別の対応策】
●個別の到達目標を設定する
その子でもできそうな目標を設定し、スモールステップで、自信を失わせないで取り組ませるようにしましょう。
例えば、マット運動で、いきなり前転から始めるのではなく、まずは、マットの上を、ごろごろと転がる運動から始めたり、縄跳びで、まずは片手で回すことから始めたりするなどです。
●ボディーイメージをつくるための活動
ボディーイメージをつくるのに、有効な活動をいくつか紹介します。
①机やハードルの下など狭い所を通り抜ける
②転がってくるボールをバットやラケットなどで、打つ
③台の上から目標のラインに飛び降りる
④ボール送りリレー、旗揚げ
【学級全体への対応策】
●位置関係を分かりやすくする
ダンスなどでは、隊列を組んだ移動が多くなり、位置関係をなかなか覚えられない子が出てきます。
視覚的な支援が有効です。
数色のカラーコーン(コーンの上から色紙を貼るなどしてもよい)や余っている椅子などを用意し、各移動先に配置したり、番号をつけたりするなど、視覚的に分かるように工夫します。
また、一緒に移動する子を決めておき、移動の時に、声をかけてもらったり、前後ではさんだりするなど、周りの子にフォローをお願いするのもいいでしょう。
●勝敗を受け入れられるようにする
発達障害がある子のなかには、こだわりが強いという特性ゆえに、1位になれなかったことや負けたことを、極端に嫌がる子がいます。
周りの子からは、「みんな我慢しているのに」と、わがままな子と思われてしまいがちです。
普段から、多数決で少数派になっても結果を受け入れさせる、「競争は、勝つ人もいれば負ける人もいる」など事前に心の準備をさせておくことが、大切です。

今回は、以上です。
最後までご覧いただきありがとうございました。
いいね!していただけると、記事を書くときのモチベーションが上がるのでありがたいです。
このブログの内容は、月森久江先生の本を参考文献としております。
月森久江先生の講演を聞いたことがあり、私の実践とつながることが多々ありました。
よろしければご覧ください。
こんな内容を記事にしてほしいというご意見がありましたら、コメントしていただくとありがたいです。
可能な限り、お応えしていきたいです。

※この投稿はアメーバブログから移行したものです。
ぜひそちらもご覧ください。









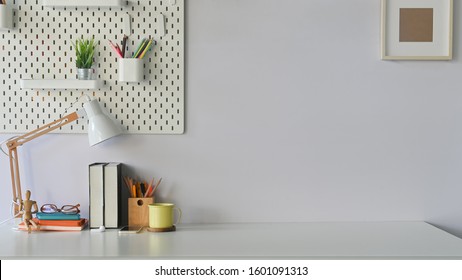


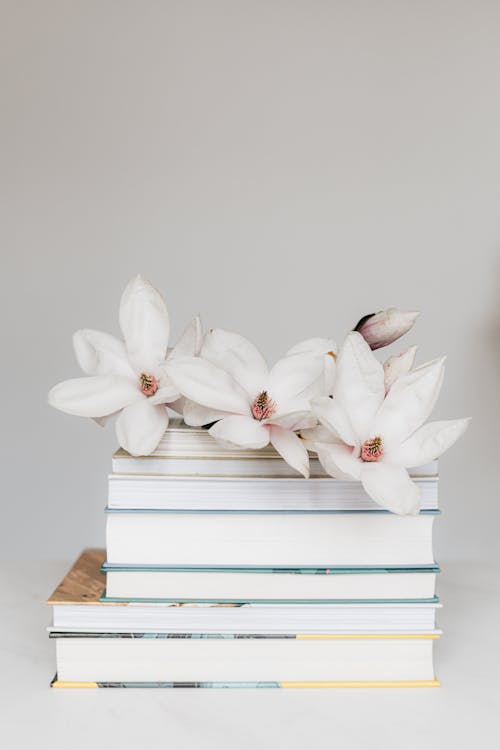

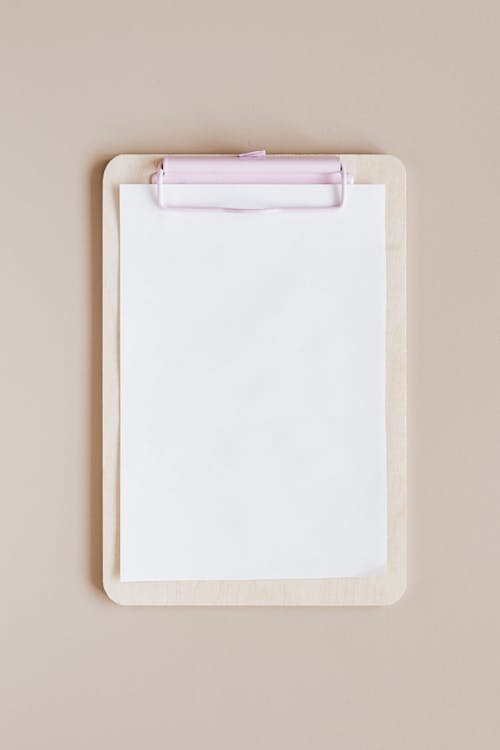

 いいねしていただけると、記事を書くときのモチベーションが上がるのでありがたいです。
いいねしていただけると、記事を書くときのモチベーションが上がるのでありがたいです。

